
-
葬儀の種類・宗派
-
神式のお葬式で知っておきたい香典袋のマナーは?参列時のマナーや作法を紹介

二礼二拍手一礼は、二礼・二拍・一礼から成る神社での参拝作法です。
頻繁に神社に行かない人にとっては、二礼二拍手一礼で具体的に何をすれば良いのかわからない人もいるのではないでしょうか。
この記事では、二礼二拍手一礼とは、参拝の流れ、いつから始まったか、行う理由、形式、例外、マナーについて詳しく解説します。

ここでは、神社で行われる二礼二拍手一礼について詳しく解説します。
二礼二拍手一礼は、それぞれ以下の動作を表します。
二礼二拍手一礼は、動作ごとに意味を持っているため、二礼だけする、二拍手だけする、一礼だけするというような参拝の流れはマナー違反です。
以上の動作には神様への感謝と敬意を表す意味だったり、邪気を払う意味だったりが込められているため、最初から最後まで滞りなく行うのが正しい方法といえます。
より正確には一拝・祈念・二拝・四拍手・一拝が正しいとされることもありますが、現代では二礼二拍手一礼でも十分丁寧なやり方です。
なお、他の記事では参拝について解説しているため、あわせて参考にしてみてください。⇒今さら聞けない参拝とは?知っておくべき意味や作法の基本を徹底解説!
神社の参拝では鈴を鳴らした後に二礼二拍手一礼しますが、お賽銭を入れるタイミングは二礼二拍手一礼の前とされるのが一般的です。
基本的にお賽銭は投げ入れるのではなく、差し出すように入れるのが作法となります。
お賽銭は神様へのお供え物として捉えられるため、放り投げるのではなく滑り入れるように丁寧に入れるようにしてください。
なお、お賽銭の金額に決まりはなく気持ちで良いとされていますが、ご縁という意味で5円を入れたり見通しが良いという意味で50円を入れたりするのが良いです。
神社の参拝では二礼二拍手一礼を行いますが、お願いのタイミングは二礼二拍手一礼の最中が適切とされています。
具体的には二拍のところで手を合わせた瞬間に、願いを唱えるのが礼儀です。
お願いは恐れ恐れ申し上げるという気持ちで行うため、頭を上げたまま行うのではなく下げた状態で行うようにしましょう。
なお、お願いの内容に特に決まりはありませんが、長時間かけずに簡潔に済ませるのがマナーです。
二礼二拍手一礼の手の位置は、胸のところに持ってきます。
なお、拍手では左手をやや下、右手をやや上(指の第一関節ほど)という具合に若干ずらして胸の前で手を叩くようにするのがマナーです。
拍手を2回行ってから手を合わせ、心を込めてお祈りします。
最後に深くお辞儀をしたら完了です。
二礼二拍手一礼の読み方は、「にれいにはくしゅいちれい」です。
神社によっては二拝二拍一拝と表現し、「にはいにはくしゅいっぱい」と読むことがあります。
世間一般には二拝二拍一拝よりも二礼二拍手一礼がよく使用されているものの、神社に合わせて使用するのが良いでしょう。

二礼二拍手一礼では、口と手を清めてお賽銭を入れ、鐘を鳴らしてから行うのがマナーです。
ここでは、二礼二拍手一礼による参拝の流れについて詳しく解説します。
神社に到着したら、まずは手水舎(てみずしゃ/てみずや)で口と手を清めます。
手水舎では柄杓に入れた水で口をすすいだり、手を洗ったりして身を清めるのがマナーです。
身を清めずにいきなり参拝するのは神様に対して失礼に当たるため、必ず神社に到着したら手水舎に行き、口と手を清めてください。
手水舎では一度お辞儀をし、柄杓を右手で持って水を満杯にし、左手に流しかけて清めるのが一般的です。その後、基本的には左手に持ち替えて右手に水を流しかけて清めます。
途中、この動作で手に水を流しかけた際、手に入っている水で一緒に口をすすぎます。
残った水で柄杓の柄の部分を洗い、元に戻せば完了です。なお、立ち去る際もお辞儀しましょう。
身を清めてお賽銭箱の前に来たら、お賽銭を入れます。
お賽銭は財布から取り出して入れる形でも構いませんが、参拝客が並んでいる場合は先に小銭を出しておき、すぐに入れられるようにしておくと良いです。
お賽銭を入れる際は投げ入れるのではなく、置いてくるようなイメージで入れてください。
お賽銭を入れたら、鐘を鳴らし二礼します。
神様への感謝と敬意を表すお辞儀は2回行うのがマナーで、腰はおおよそ90度に曲げて通常のお辞儀よりも深く行うのが作法です。
なお、混雑している場合は、鐘を鳴らすことにこだわらず、迅速に済ませられるようにするのが良いでしょう。
鐘を鳴らし二礼したら、二拍手をします。
邪気払いを表す拍手も2回行うのがマナーで、手を打つ際は左手と右手をややずらして打つのが礼儀です。
なお、神社によっては4回手を叩くところもあるため、参拝する神社の慣習に合わせて行うようにするのが良いでしょう。
二拍手をしたら、お願いをします。
お願いの内容はどのようなものでも差し支えありませんが、「家族が健康でいられますように」「仕事がうまくいきますように」といった日常生活に関するものが主流です。
逆に「お金持ちになれますように」「海外旅行に行けますように」というような俗物的なお願いは行わないのがマナーといえるでしょう。
神社の参拝でのお願いは、あくまでも恐る恐る行うもの。いずれにせよ、神様に対して尊ぶ気持ちを大切にしなければいけません。
お願いをしたら、一礼をします。
腰を90度に曲げてお辞儀を行い、他の参拝客の迷惑にならないように立ち去ります。
なお、お辞儀は会釈程度で良いとされることもあるため、必ずしも90度まで腰を曲げる必要はありませんが、どちらにせよ、神様に対してきちんとお辞儀をするのがマナーです。
お辞儀をせずに立ち去るのは神様に対して失礼に当たるため、注意が必要です。

二礼二拍手一礼は、明治8年に式部寮から頒布された官国幣社の祈年祭に関する事項を定めた神社祭式に、再拝拍手と記されたところから始まっています。
再拝拍手から始まり、再拝・祝詞奏上・再拝や再拝・祝詞奏上・再拝・二拍手・一拝など、祭事を任された人物、定義づけした機関によって、新たなやり方の改良や考案が行われていきました。
後の明治40年に神社祭式行事作法が制定され、ようやく作法が定義されました。
当時は再拝・二拍手・押し合せ・祝詞奏上・押し合せ・二拍手・再拝という形式となっており、現在の二礼二拍手一礼という作法よりも複雑な動作が必要だったとされています。
その後、式の円滑な進行や思考の変化から、神社祭式行事作法に幾度かの改訂が行われ、昭和23年に改訂された段階で二礼二拍手一礼が正式な参拝作法となったわけです。
先人による永きに渡る改訂、そして神様を尊う心によって作られたのが、二礼二拍手一礼というわけです。

二礼二拍手一礼は、もともと神様に対して感謝や敬意を持つ考え方があったと推測されますが、参拝作法としては神社祭式に記載された再拝拍手の考え方から始まっているとされています。
対して、当時の人々はどのタイミングで再拝拍手を行うのかわからなかったとされています。
曖昧な状態で再拝拍手が広まっていくなか、内務卿を担当していた伊藤博文から一揖・再拝・二拍手・一揖が正式な作法であると語られたところから、当時は一揖・再拝・二拍手・一揖が正しいやり方として、世間に広まったといえるでしょう。
その後、1882年8月に明治政府から神道政策の一環として、古典(国典)研究および神官養成を目的とした機関で、神道総裁有栖川宮幟仁親王が皇典講究所総裁となった皇典講究所が設立されました。
ここで再拝・祝詞奏上・再拝・二拍手・一拝という指導が行われ、世間に広まりました。
つまり、伊藤博文から伝わった一揖・再拝・二拍手・一揖に変わって、再拝・祝詞奏上・再拝・二拍手・一揖が正しいマナーとして行事等で実施されるようになったわけです。
一時期、再拝・二拍手・押し合せ・祝詞奏上・押し合せ・二拍手・再拝など、従来の参拝作法を原型として、動作の追加も見られましたが、昭和23年に神社祭式行事作法が改訂され、現在の二礼二拍手一礼になったというのが通説です。
例外的に一拝がなかった時期もありましたが、皇典講究所から終わりの一拝がないと締まらないという指導があったことで、二礼二拍手一礼が定着しました。
上記の言い渡しを考えると神様を敬うだけでなく、どういう形式で進んでいけば式が円滑に進められるかも考慮された結果として、現在の二礼二拍手一礼の形式になったと推測できるのではないでしょうか。

二礼二拍手一礼は、出雲大社や伊勢神宮などで例外が見られるため、注意が必要です。
ここでは、二礼二拍手一礼の例外について詳しく解説します。
出雲大社では、以下のような参拝作法が主流となっています。
出雲大社の公式ホームページにも記載がある通り、同神社では二礼四拍手一礼が正式な参拝方法となっており、大分県の宇佐神宮や新潟県の弥彦神社も同様です。
一般的な神社では二礼二拍手一礼が基本的な参拝作法とされているものの、出雲大社をはじめとする一部の神社では例外があることを忘れてはなりません。
なお、出雲大社で毎年5月14日に開催される例祭(勅祭)では、特別に二礼八拍手一礼が行われるなど、特別な行事の間だけ参拝の方法が変わることもあります。
もし出雲大社を参拝する場合は、出雲大社でのやり方を守るのがマナーです。
伊勢神宮では、恒例祭や神宮祭祀など、精進潔斎を行った神職が八度拝八開手という四拍手を2回行う参拝方法で行事を遂行する場合があります。
普通の参拝客は通例通り二礼二拍手一礼で問題ないとされているものの、行事によっては例外があると知っておくだけでも安心です。
ここまで解説してきたように、神社によって参拝のマナーが変わることがあるため、訪れる神社に関してはよく調べておくのが良いでしょう。

二礼二拍手一礼は、感謝と敬意の心を示すこと、邪気を払うために音を鳴らす、長居せず手短に済ませる、割り込んで参拝しないのがマナーです。
ここでは、二礼二拍手一礼のマナーについて詳しく解説します。
二礼二拍手一礼は、神様に対して感謝と敬意の心を示すためのものです。
心を込めずに適当に参拝するなど、神様に対して心が込もっていないのはマナー違反となるため、何のために参拝するのかを今一度考えておくことが求められます。
神社を参拝する理由としては、日頃見守ってくれている神様に対して感謝や敬意を伝えるだけでなく、穢れを清めたり願いを唱えたりする意味合いもあります。
人によっては開運招福や合格祈願、商売繫盛や無病息災など、色んな願い事があるはずです。
こうした願いを神様に届け、祈願するための行為が参拝といえるでしょう。
そのため、ただ適当に行うのではなく、感謝と敬意の心を示すのがマナーとなるでしょう。
二礼二拍手一礼は、邪気を払うために音を鳴らすのがマナーです。
手を叩く際、他の参拝客に気を遣ってあまり音を立てないようにする人もいますが、二礼二拍手一礼ではむしろ音を立てるようにして手を叩きます。
音を立てることで邪気が払われるとされているため、遠慮する必要はありません。
むしろ、手を叩いて音を鳴らすことが邪気払いになるといえるでしょう。
神社を訪れた際は鳥居をくぐることになりますが、鳥居ではくぐり方にも注意が必要です。
神社を訪れて鳥居をくぐる際は、一礼をするのがマナーとされています。
また、参道の中央は神様が通る道とされているため、真ん中ではなく端を歩くのが古来の参拝作法とされています。訳あって参道の中央を横切る場合は、会釈するのがマナーです。
鳥居をくぐる際は行きだけでなく帰りも一礼するのがマナーとされるため、最初から最後まで気を抜かずに対応するのが良いでしょう。
二礼二拍手一礼では、長居せずに手短に済ませるのがマナーとなります。願い事をしばらく唱えている人も稀に見られますが、心のなかで一度伝えたらそれで十分です。
むしろ、いくつもの願いを伝えるのは神様に対して失礼に当たることがあるため、二礼二拍手一礼はスムーズに終えられるようにしてください。
二礼二拍手一礼では、割り込んで参拝しないのもマナーです。参拝客の行列への割り込み、いわゆる横入りは他の人の迷惑になります。
参拝する場合は正面から入り、列に並んで自分の番を待つのがマナーとされるため、割り込みはやめましょう。
もちろん、誰かに並んでおいてもらって後から入るのもお避けください。何がトラブルになるかわからないため、ルール違反はしないようにしましょう。
普段何気なくやっている神社の参拝ですが、二礼二拍手一礼を正しい方法でできないとマナー違反となるため、参拝前に改めて確認しておくと安心です。
参拝だけでなく、お葬式などでも参拝作法が重んじられるため、社会人は正しいやり方を身につけておくことが欠かせません。
当記事で解説した内容は生涯にわたって使用できるため、何度も読み返しながら勉強しておくと実際の参拝でも役立ちます。
対して、お葬式などは複雑な手続きが必要で何から行えば良いかわからないという人もいるため、もしお葬式が必要となった人で何から手配すべきかわからない人は、一度よりそうお葬式にご相談ください。
当社では、全国各地のお葬式の手配に対応しています。一般葬に加えて家族葬や火葬式にも対応しており、故人さまはもちろん喪主やご遺族のご意向に合わせたお葬式が可能です。
まずは、よりそうお葬式の公式ホームページをご覧ください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀の種類・宗派
神式のお葬式で知っておきたい香典袋のマナーは?参列時のマナーや作法を紹介

葬儀の種類・宗派
一般葬とは?参列者の範囲やメリット・デメリットなどを解説!

葬儀の種類・宗派
死装束は好きな服を選べる?注意点や宗派ごとの違いを解説

葬儀の種類・宗派
一日葬とは?5つのメリットと3つのデメリットを詳しく解説!
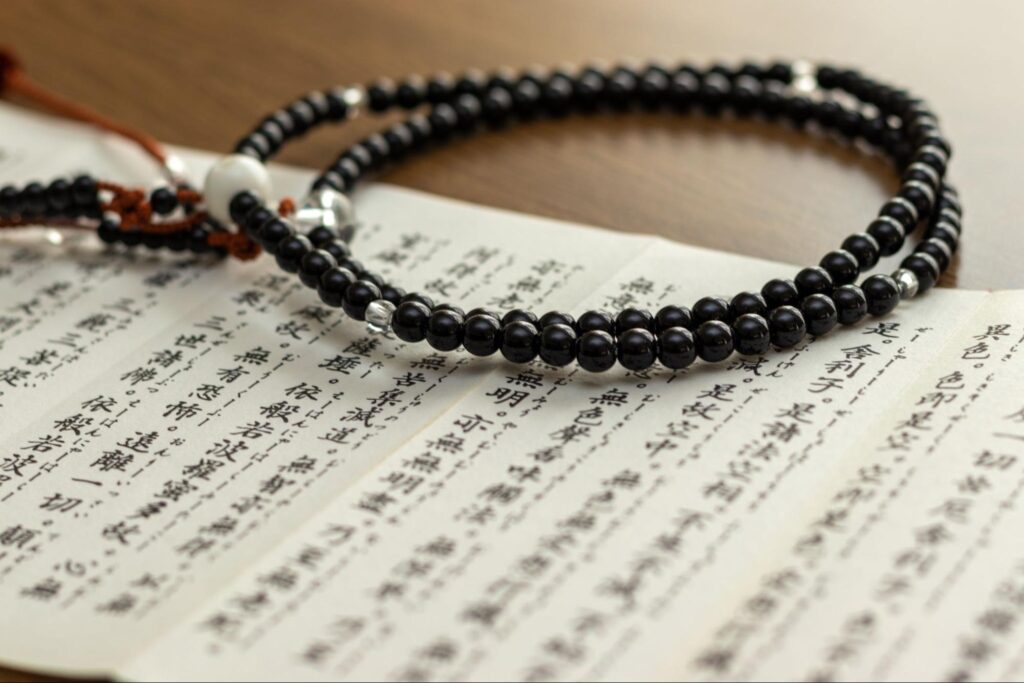
葬儀の種類・宗派
浄土真宗のお経の由来は?宗派や葬儀におけるマナーについて解説

香典の金額相場は?香典袋の書き方・渡し方やマナーまで徹底解説

香典の金額が五千円の場合の書き方は?縦書き・横書きについて詳しく解説

二七日・三七日・四七日・五七日・六七日・七七日法要について

お葬式に参列できなかった!時間が経ってからのお悔やみの伝え方は?贈り物は?

不動明王とは?真言の唱え方や効果などについて

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方
横にスクロールできます

津川雅彦さんと朝丘雪路さんの葬儀・お別れの形 | 「ご夫婦合同のお別れの会」は華やかな人生の千秋楽

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

仏壇のことを詳しく紹介!種類や選び方は?

仏壇の価格には幅がある!選ぶ基準は?

お通夜に持参する香典のマナー!

仏壇には何をお供えする?注意点は?
横にスクロールできます